オークの首に残る、不穏な古い傷跡。
横一文字に走った鋭い太刀傷は、まるで斬首のよう。
「そう、首を刎ねたんだよ」
不躾な視線に気を悪くした風もなく、オークは剣を模した右手でスッと首を横切った。
「切るんならここが一番確実だと思ってね」
「自分でやったのか?」
「ああ。だけど失敗した。首じゃなくて心臓を一突きにしていたら、紋章も邪魔できなかったかなぁ」
他人事のようにさらりと、笑いながら自分殺しを口にする。
終わった事なのか、それとも現在進行形か。
視線に込めた問いを悟って、オークが哂った。癖のある長い前髪に、深海の青が片方だけ隠れた。
「切ったのは一回だけだよ。もうしない。俺は一緒に行けなかった。置いて行かれた。チャンスは一度だけだった。乗り遅れた馬車を追いかけるつもりはない」
「チャンス?」
「一緒に埋葬して貰えるんならって思ったのさ」
眇めた瞳が、目の前の風景を通り越して遠い過去を視る。
「墓の中まで付いてくるなって追い返されたのかもね」
「確かに。眠る時位は静かにしてやるべきだ」
「ひどいなぁ。俺はそんな騒がしくないだろー」
笑いながら、無残な傷跡が黒のタートルの下に隠されていく。
着衣の際に喉元を滑った指の動きが、宝物に触れるように優しく繊細だった事に腹が立った。
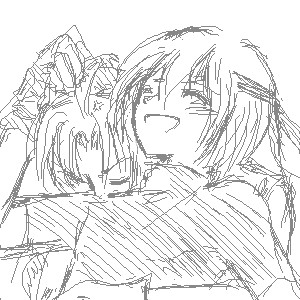
「あはは、くすぐったいって!」
背後から抱きしめ、服に覆われた細い首筋に唇を落とす。
軽く歯を立てると、髪を掴まれたが、引き剥がそうとする気配はなかった。
「………いい加減、その空元気を止めろ」
「何言ってるのさ。俺は元気だよー」
「…………(ムッ)」
オークが落ち込めば落ち込むほど明るくなるということは、短くない付き合いで分かっていた。
オークは未だ150年前からの想い人を忘れていない。こうして自分の腕の中にいても、心はスノウだけを追い求めている。
自分はスノウの身代わりだという事は、嫌と言う程分かっていた。
そしてオークが、自分のそんな気持ちを知っていて甘えてくることも。
「……ありがとうね」
軟らかい髪が、そっと頬を擽った。
気まぐれ猫が甘えてくるような仕草で。
「君がいるから、今俺は笑えてる。それは嘘じゃない。ほんと、感謝してる。ありがとう」
「……どういたしまして」
間抜けな返答の上、こんな言葉で簡単に機嫌を直してしまう自分に、我ながら呆れつつ。
抱きしめる腕に力を込めた。

